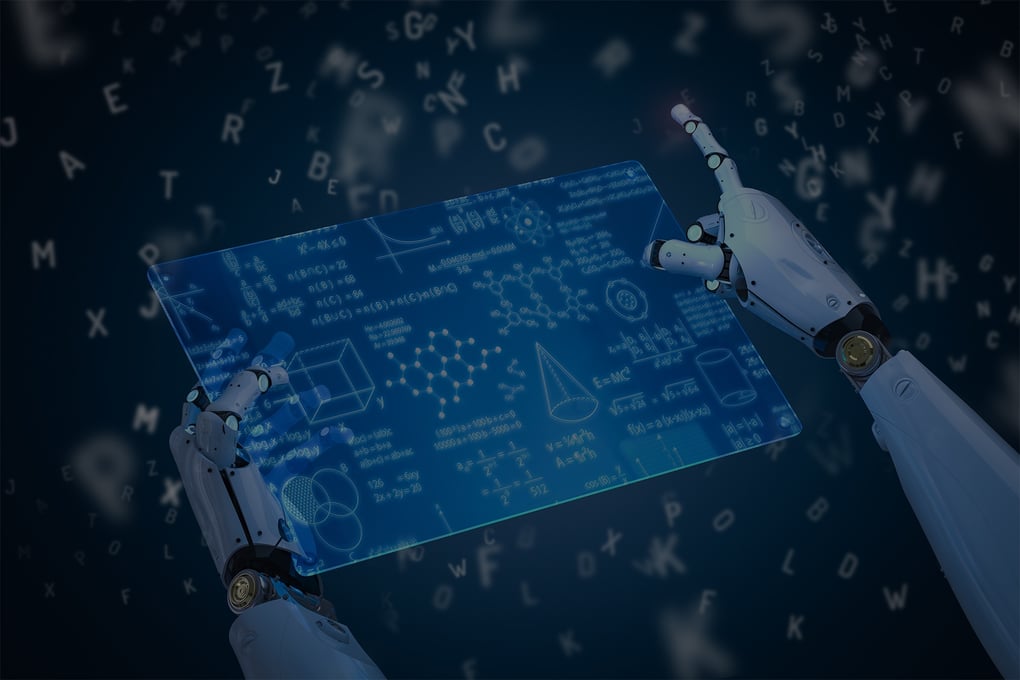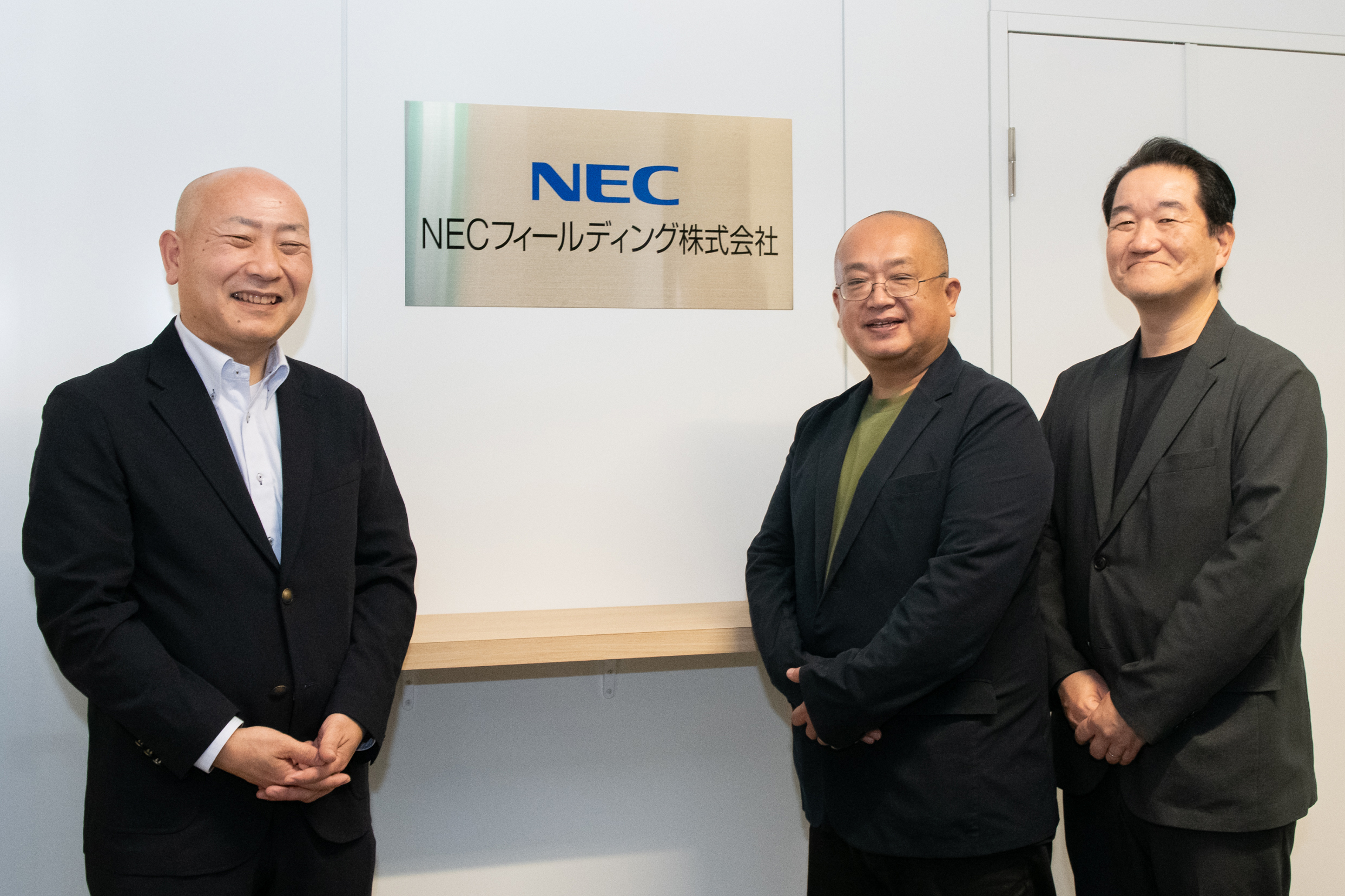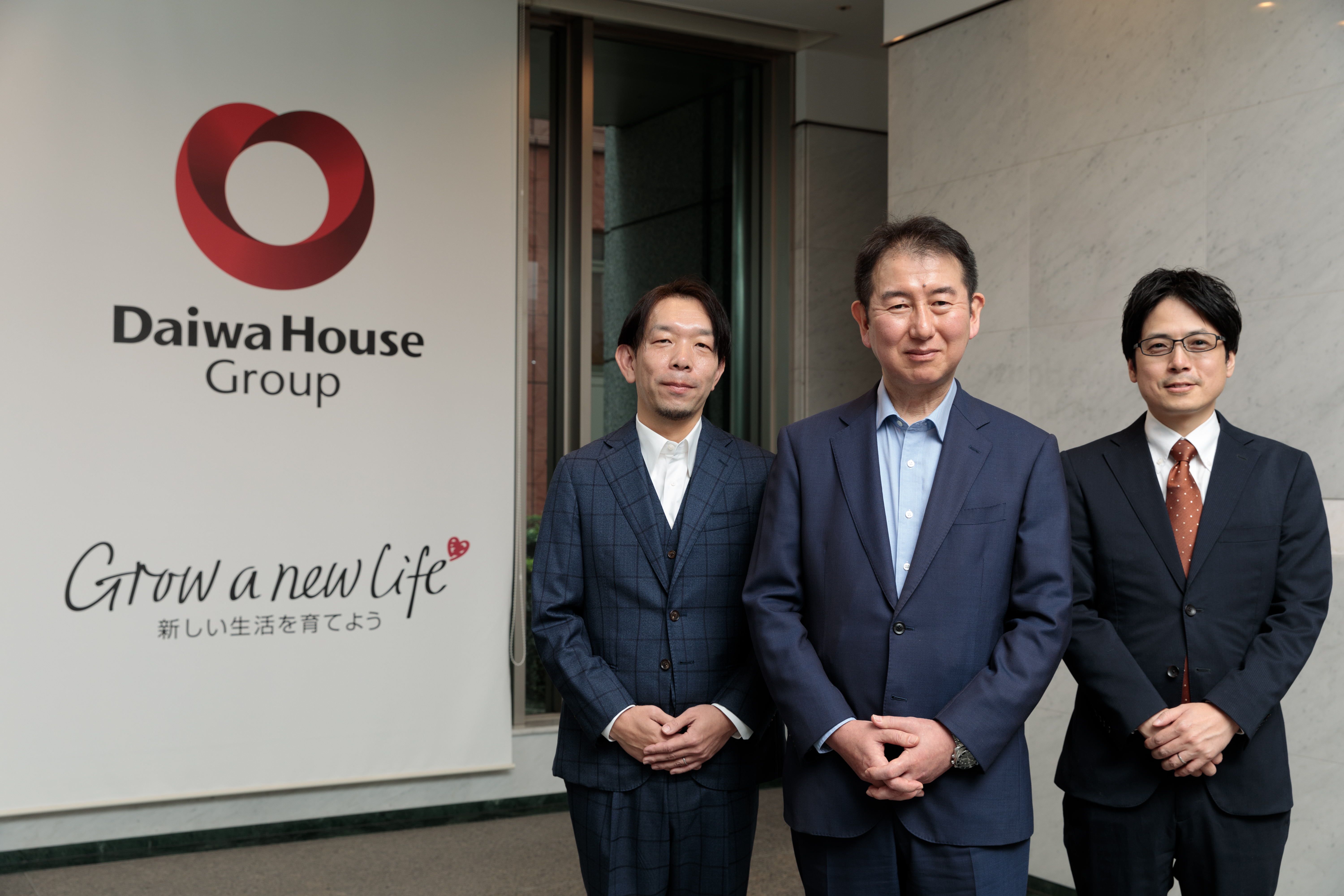概要
資産管理サービス信託銀行
金融機関をはじめ機関投資家の有価証券の管理を担うみずほフィナンシャルグループの資産管理サービス信託銀行(以下、TCSB)にとって、日々の事務処理そのものが商品であり、その生産性を追求することが、競争力の強化に直結する。同社では全社レベルでRPAの普及活用を図るために、デジタル・イノベーション推進室を設置し、現場の業務をRPA化できる“DIクリエイター”の育成に取り組んでいる。
“事務”自体が商品だからこそ徹底して生産性にこだわる
低金利時代にあって機関投資家の運用は急速に多様化している。対象となる運用商品を増やしたり、新たな投資対象国を追加するなど、あらゆるベクトルに運用形態が拡大している。金融機関の有価証券運用の管理を手がけるTCSBが提供する業務も、こうした変化に対応して、多様化の一途をたどっている。
「当社にとって、事務処理は商品そのもの。品質を確保しながら生産性をいかに上げるかは常に重要な経営課題です」と常務執行役員の吉田昌史氏は語る。TCSBは、これまでもセンターシステムの活用のみならず、エンドユーザーコンピューティングを導入するなど、事務処理の生産性向上に取り組んできた。事務処理業務の生産性を高めることが、同社の競争力を左右する。
そんな同社がRPAに注目したのは、当然の流れだと言えるかもしれない。吉田氏は「定型業務大量処理ではなく、多様化し変化し続けるニーズにスピーディに対応するには、これまでの業務改善のアプローチでは一定の限界があります。そこでこれからの武器としてAIやRPAに注目しました」と話す。
ビジネス環境が激しく変化している金融業界のニーズに対応するには、2つの観点から生産性を向上させる必要がある。迅速に対応できる体制を構築することと、コスト面で競争力のある商品を提供することだ。この2つの課題を解決するテクノロジーとして着目したのが、RPAとAIの活用であり、その試みはまずRPAから始まった。

常務執行役員 吉田 昌史氏
ロボットの内製化を前提にベンダーの選定に臨む
TCSBがRPAと最初に接点を持ったのは、2017年1月のことだ。きっかけとなったのは、もともと付き合いのあるシステムベンダーからの紹介だった。まずRPAのコンセプトを理解し、事務系の業務に適用できるかをイメージするために、社内で説明会を実施した。説明会には担当役員も出席。その上でRFPを作成して取引のあるシステムベンダー5社に提示した。
同社のアプローチの大きなポイントは、社員にロボットを作成させる内製化を前提としたことだ。「業務自体は右肩上がりで増えています。増え続ける業務量に対応するには、業務フローを効率化していかなければなりません。RPAはそれを実現するための武器であり、当社の競争力強化につながる、価値あるスキルだと考えたからです」と吉田氏は語る。
どうRPAを導入していくのかという点についても、内製化を実現できるかどうかという視点から考えた。同社ではRFPをRPAベンダーに直接提示するのではなく、複数のRPAツールを扱っているシステムベンダーに提示している。RPAの機能とあわせて社内向けの支援体制も重視したからだ。
RPAを推進する中心的な役割を担う事務統括部デジタル・イノベーション推進室の室長である中村博充氏は「教育研修をしっかりやってくれるのか、トータルのコストは適正なのか、常駐してフォローする体制を用意してくれるのか、といった点から選定しました。RPAは新しいソリューションなので導入実績はそれほど重要視しませんでした」と話す。
使い勝手と柔軟性からUiPathの導入を決定
TCSBでは、2017年の1月からRFPを各社に提示し、3月にRPA化を推進するパートナーを選定した。3月末にはデジタル・イノベーションチームを立ち上げ、全社レベルの導入プロジェクトをスタートさせ、4月から具体的なRPAツールの選定に入った。
そこでの選定のポイントは、ユーザーが使う上での親しみやすさと、多様なシステムに対応できる柔軟性だった。
事務統括部長の中田仁志氏は「社内には年金系や信託系などの様々なシステムが混在し、社内のSEが構築したエンドユーザーコンピューティングツールも多数あります。これらのシステムに対応できて、連携させられることが条件でした」とRPAツール選定のポイントを上げる。
その結果、同社が選定したのはUiPathだった。決め手になったのは、UiPathのレコーディング機能である。中村氏は「当時はレコーディング機能を実現していたRPAツールは少なく、これから開発するという製品ベンダーがほとんどでした」と振り返る。
UiPathであれば、業務によるOSがバラバラでも、操作画面をレコーディングすることでロボットを作成できる。基幹系システムの操作も取り込めて、分散型のシステムとのデータ連携も可能だ。この機能の有無はロボットの作りやすさも左右するだけに、内製化には欠かせない機能だった。5月にはUiPathの導入を決定した。

事務統括部長 中田 仁志氏
各部門から人材を集めてDIクリエイターを育成
RPAの導入プロジェクトの鍵を握っていたのは、ロボットを作成できる社員をいかに育成するかだった。デジタル・イノベーションプロジェクトチームは、ユーザー部門のロボット作成者を、デジタル・イノベーションを創造する“DIクリエイター”と定義し、各ユーザー部門に協力を求めた。
第1期生としては、各部から1~2名程度の人材を出してもらい、約10名を対象に2017年の5月から9月まで育成に取り組んだ。最初は座学で講義を行い、6月からは缶詰状態で実践的なトレーニングを開始。トレーニングは一回半日で2ヶ月間行われ、8月からは現場に戻ってロボット作成に取り組むことを目標に定めた。
プロジェクトの事務局を務めた事務統括部デジタル・イノベーション推進室の福田麻美氏は「パートナーと一緒に育成計画を立案し、トレーニングに取り組みました。トレーニングプログラムも手探り状態でしたが、まずは全体を3つのグループに分けて、グループごとにトレーナーをつける少人数制で進めていきました」と話す。
実際にトレーニングを進めていくうちに、DIクリエイターの得意分野が明確になってきた。ロボットを作成するのが得意な人と、業務を分析・整理するのが得意な人たちだ。「ロジカルに考えることができるかどうか、ITリテラシーが高いかも重要ですが、それぞれがもつ得意分野を活かし協力することが効率的なロボ作成のポイントだと感じています。」(福田氏)。
研修を終え現場に戻ったDIクリエイターたちが、本番用にロボットを作成しだしたのは8月頃からだった。福田氏は「これまでシステムに手入力していた作業をロボットに置き換えるというのが、効果としてわかりやすいので、最初はそういう案件を選んで取り組んでもらいました」と振り返る。そこからロボットの活用が始まった。
金融共通の課題である時間的な制約からの解放
ただし、当初から全てのケースで期待された効果が得られた訳ではない。うまくいかなかった場合も含めて、まずやってみて改良を繰り返すという試行錯誤をしながら進めていったという。
吉田氏は「どの業務をロボットに置き換えるのかを含めて、現在進行形でノウハウを蓄積しています。昨年度はロボットの導入期であり、RPAを知る期間でした。これからはロボットを使って事務プロセスを見直し、効果の最大化追求していきたい」と話す。
実はこの業務プロセス自体を見直していくというのが、内製化の最大の狙いでもある。中村氏は「実際に業務をやっている人たちが、そもそもこの業務の進め方はこれで良いのだろうかと考えながらロボットを作ることで、業務改革が進んでいくはずです」と期待を語る。
すでに入力系では大きな効果が現れ始めている。事務処理の正確性を求められる同社では入力系作業結果のチェックに“三鑑体制”を取り入れている。ある担当者が入力した内容を別の担当者がチェックし、さらに第三の担当者がチェックするという、トリプルチェックを行ってきた。そこにロボットを導入して、マンパワーの削減と時間の短縮を図ることができた。
また、複雑な事務プロセスを見える化し、作業をロボットに置き換えることで、誰もがその事務に対応できるようになるという効果も見えてきている。「基幹システムやエンドユーザーコンピューティングシステムの操作はどうしても属人的になっています。今までベテランの頭の中にあった複雑な操作をロジック化してロボットに置き換えることで、ミスも減らすことができます」(中田氏)。
「さらに大きな効果は、時間的なプレッシャーから担当者を解放できることです。早朝時間に定期的に行っていた集計やデータ収集の業務をロボットに行わせることで、早朝出社する必要がなくなるといったメリットが得られています」と吉田氏。時間との戦いは金融業界共通の課題だけに、他社でも大いに参考になるはずだ。

事務統括部デジタル・イノベーション推進室 室長 中村 博充氏
自由度を確保しながらロボット活用環境を整備
TCSBでは2018年3月末時点で60を超えるロボットが活用され、現在も続々と増えつつある、ロボットを作成するDIクリエイターの育成も順調だ。昨年10月にスタートした第2期生26名の研修が今年4月に完了し、現在、第3期生のトレーニングが行われている。
「事務に携わっているほとんどの人は、少しでも事務を改善したいという意識を持っています。その手段の一つであるロボットに興味を持っている人は多いですね」と福田氏。

事務統括部 デジタル・イノベーション推進室 福田 麻美氏
同時に、野良ロボットが生まれないための対策も講じられている。作ったロボットは申請書や台帳で管理するといったルールも取り決めた。「ただ、がんじがらめにはしないように、必要なドキュメントを必要最低限にスリム化するなど、既存のシステムとは異なるルールを設けて、機動性を確保しています」と中田氏。
共に働く仲間としてのロボットの位置付けも進められている。中村氏は「ロボットをデジタルレイバーと置き換えました。システムリスクの部門のメンバーと協議して、ロボットに与えるIDの考え方やロボットにはやらせない業務を決めるなど利便性とシステムリスクの両面から許容範囲を決めています」と話す。
中田氏は「DIクリエイターの育成は当面60名が目処。彼ら彼女らが主体となって自律的にロボットを作成し、業務カイゼンを進めてくれるようになることを目指しています」と話す。事務統括部内に今年4月に立ち上げた、デジタル・イノベーション推進室が、人材育成やブランディング、ロボットの管理などを行う。モジュールを共通パーツとして提供することなども含む。
社内的な認定制度や表彰制度も整備した。DIクリエイターを習熟度によって「ブロンズ」「プラチナ」「ダイヤモンド」の3階層にわけ、ロボット活用で優れた事案は社内で表彰している。2017年下期からスタートして、全体で10件弱が選ばれ、大賞も2件でている。
吉田氏は「ロボットを活用する目的は、効率化だけではありません。事務フローを再設計して、BPRに取り組む機会でもあります。ロボットに任せるプロセスを長くしたり、洗練させることで、大きな効果が得られるはずです」と語った。UiPathには、事務の効率化や品質向上へのますますの貢献が期待されているのである。